ジョージ・ホワイトフィールド・チャドウィック(1854〜1931)の音楽
マーチ王スーサと同じ年に生まれたチャドウィックは、ニューイングランド音楽院で専門教育を受けた後に、一時はミシガンにある大学の教師に就くが、ヨーロッパに渡ってより専門的に作曲を勉強することを志す。農民出身の父親はこれに反対したが、結局はベルリン、ライプツィヒ、ミュンヘンと、3年間ドイツ各地で学び、帰国。亡くなるまで母校ニューイングランド音楽院の院長を勤めた。
あらゆるジャンルに作品を残しているが、第2交響曲では南部民謡を使った箇所もあるといわれ(よく引き合いに出されるのは第2楽章)、母国の素材を使用した点ではアイヴズに先んじていたことを指摘する学者もいる。また、世紀末フランスの作曲家たちからの影響もあったとされ、交響詩《タモ・シャンター》では、色彩豊かな管弦楽法と濃い和声も垣間見られる。ヨーロッパではフランス・アカデミズムに対する関心も強く、セザール・フランクに師事することも考えていたが実現せず。1905年には、ヴァンサン・ダンディを招いて、自作を指揮させる企画もした(これも実現せず)。
作風は自由奔放で、ペインやパーカーなどよりもずっとあか抜けた感じがする。また、国民楽派的な影響も見られ、大胆な管弦楽法が聞かせる一方、フォスター風のほっとする響きが聴かれたりもする。また、初期の室内楽作品や交響曲第2番は、アメリカに滞在したドヴォルザークにも聴かれたのではないかとも察せられている(第3交響曲は、ドヴォルザークも審査員を務めていたコンクールで賞を獲得)。
彼の資料のほとんどはニューイングランド音楽院に大切に保存されている。ここ10年ばかり、やたらと注目されている作曲家のようだ。Reference Recordingsから作品集が2枚。ヤルヴィが交響曲2・3番を録音(英シャンドス)。ハンソンが《シンフォニック・スケッチズ》をマーキュリーに録音していたのもCDになっている。室内楽は、かつて米Northeasternから数枚出されていた。(02.1.4.)
リップ・ヴァン・ウィンクル序曲
ネーメ・ヤルヴィ指揮デトロイト交響楽団 英シャンドス(CD)CHAN 9439
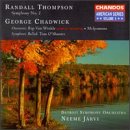 チャドウィックがハンブルク音楽院の卒業作品として作曲したもの。この作品でチャドウィックは第1位を得ただけでなく、初演を聴いたドイツの批評家から熱列な支持を受けた。1879年、まだ作曲者がハンブルクにいる間に、ボストンのオーケストラによってアメリカでも演奏され、チャドウィックの作曲家としての名声を確立した。ワシントン・アーヴィングの『スケッチブック』に収められている短編「リップ・ヴァン・ヴィンクル」が土台になっているが、チャドウィックが実際に影響を受けたのは19世紀後半に見たジョセフ・ジェファーソンの演劇版と思われる(実際、献呈者はジェファーソン)。
チャドウィックがハンブルク音楽院の卒業作品として作曲したもの。この作品でチャドウィックは第1位を得ただけでなく、初演を聴いたドイツの批評家から熱列な支持を受けた。1879年、まだ作曲者がハンブルクにいる間に、ボストンのオーケストラによってアメリカでも演奏され、チャドウィックの作曲家としての名声を確立した。ワシントン・アーヴィングの『スケッチブック』に収められている短編「リップ・ヴァン・ヴィンクル」が土台になっているが、チャドウィックが実際に影響を受けたのは19世紀後半に見たジョセフ・ジェファーソンの演劇版と思われる(実際、献呈者はジェファーソン)。
物語自体はアメリカの子供にはとても有名なもの。恐妻家で気のいいリップは、村人の人気ものだったが、ある日森に出かけて不思議な亡霊に遭遇する。彼らと酒を交している間に眠りについてしまったのだが、起きたのが、実は20年も経ってからのことだった。そんなこととも知らず村に帰って見ると、南北戦争後、民主主義を高らかに歌い上げる土地には誰一人として知る人がいない。「この村にリップ・ヴァン・ヴィンクルという男はいないのか」と尋ねてみると、大きくなった自分の息子リップが現われる。ヴァン・ヴィンクル夫人はずっと前に亡くなってしまった。リップは田舎に隠居する。
演劇版では、娘のミーニーと年老いた妻グレートヒェン(原作は、単にヴァン・ヴィンクル夫人)が登場し、息子は登場しない。妻はある日、リップが若い女性と踊り飲み遊んでいたのを目撃したことから、リップを家から追い出す。しかしそれからずっと自分のしたことを後悔しつづけていた。嵐の中飛び出し20年帰ってこないリップは死んだと信じていたグレートヒェンは、デリックという男と一緒に住むが、あまりにも横暴で、娘のミーニーも嫌気がさしていた。デリックはさらに、リップのいないことをいいことに、リップの持つ土地を自分のものとしようと書類作成に翻弄する。20年後帰ってきたリップだが、その変り果てた姿に、グレートヒェン、ミーニーともに気がつかない。しかしリップの必死の説得によってミーニーが最初に父の生還を喜び、グレートヒェンもそれに続く。かくしてデリックの土地剥奪の策略も失敗に終わり、町中がリップを英雄として迎えいれる。
1930年に若干オーケストレーションが変更され、その改訂版が出版された。ヤルヴィの演奏もこの版を使っていると思われる。
曲は、序奏つきのソナタ形式。冒頭のチェロが、眠りから覚めるリップを象徴的に表現する。ホルンの響きが、ドイツ流だが、深い森を暗示しているかのようだ。テンポにドライブがかけられて、ソナタ・アレグロの主部に入る。定式通りの提示部のあと、展開部は、調が次々と展開したり短調があわられたり、最終的には不気味な和音も現われ、深く森へと入っていったリップが亡霊に遭遇する場面を表現している。展開部の最後はリップが眠りに入るかのように、静けさが訪れるが、そのあと冒頭に現われたチェロのパッセージが再びあらわれる。リップの20年後の目覚めである。この表現のために、曲は、再現部にはソナタ形式では繰り返されない序奏も繰り返される。続く接続部には今までに現われなかったリズムの刻みがかいまみられ、リップが全く違う世界にいることを予感させる。ソナタ形式は定式通りに再現されるが、コーダに第1主題と第2主題の断片が交互に現われる箇所がある。これはリップがグレートヒェンとミーニーに再開する場面(演劇版のみにあてはまる)をどうやら暗示しているようである。演劇版に従い、曲は最高潮に盛り上がりハッピーエンドになる。(1998年?)
交響曲第2番変ロ長調 作品21 ネーメ・ヤルヴィ指揮デトロイト交響楽団 英Chandos CHAN 9334
 |
第2交響曲は、もともとは管弦楽作品として書かれた作品をまとめて前半楽章とし、その後完全な4楽章形式の交響曲に練り上げた作品。1886年、作曲者指揮によるボストン交響楽団によって初演されている。
ソナタ形式による第1楽章は、序奏部のホルンと、それをもとにしたトランペットのファンファーレが進めていく。第2楽章は、アメリカ土着の素材からの影響が認められるが、素朴で楽しい音楽が展開する。これもソナタ形式によるが、不思議とスケルツォ的性格を持っている。後半楽章は、当然前半の流れを意識して書いたのだろうが、第3楽章は、5つの部分からなる重みのある音楽。第4楽章は第1楽章からきたファンファーレ風の主題を舞曲風なリズムで展開。構成力に弱いところもあるようだが(いずれスコアを入手次第確認したい)、怒濤のフィナーレも華々しく、なんとかまとめたようだ。筆者個人としては、前半楽章の面白さに、どうしても耳がいってしまったが。
同時収録は《シンフォニック・スケッチズ》。そのまま訳せば交響的スケッチ(あるいは素描)となるが、交響曲同様4つの楽章からなる管弦楽のための作品。スコアはKulmusからリプリントが出ているが、各楽章の前に、詩が添えられており、幻想的な雰囲気や、標題音楽的な意味を感じさせる(第3楽章には、シェイクスピアからの一節が引いてある)。アメリカらしさといえば第1楽章だろう。チャイコフスキー的な冒頭部分が終わると、ホルンのファンファーレとともに、いきなりフォスター的な雰囲気が広がり、やさしい第2主題が出てくる。管弦楽法的な色彩感では、第2交響曲よりも、ずっと広がった感じがする。
ハワード・ハンソンもイーストマン・ロチェスター管弦楽団とこの作品をマーキュリーに録音しているが、ヤルヴィのは、それよりもずっとしっくりとしたまとめ方で、古典的な管弦楽作品としての感触があるように思う。(02.1.6.) |
作曲家リストに戻る
メインのページに戻る
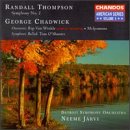 チャドウィックがハンブルク音楽院の卒業作品として作曲したもの。この作品でチャドウィックは第1位を得ただけでなく、初演を聴いたドイツの批評家から熱列な支持を受けた。1879年、まだ作曲者がハンブルクにいる間に、ボストンのオーケストラによってアメリカでも演奏され、チャドウィックの作曲家としての名声を確立した。ワシントン・アーヴィングの『スケッチブック』に収められている短編「リップ・ヴァン・ヴィンクル」が土台になっているが、チャドウィックが実際に影響を受けたのは19世紀後半に見たジョセフ・ジェファーソンの演劇版と思われる(実際、献呈者はジェファーソン)。
チャドウィックがハンブルク音楽院の卒業作品として作曲したもの。この作品でチャドウィックは第1位を得ただけでなく、初演を聴いたドイツの批評家から熱列な支持を受けた。1879年、まだ作曲者がハンブルクにいる間に、ボストンのオーケストラによってアメリカでも演奏され、チャドウィックの作曲家としての名声を確立した。ワシントン・アーヴィングの『スケッチブック』に収められている短編「リップ・ヴァン・ヴィンクル」が土台になっているが、チャドウィックが実際に影響を受けたのは19世紀後半に見たジョセフ・ジェファーソンの演劇版と思われる(実際、献呈者はジェファーソン)。
